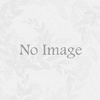本を読むのには体力が必要

昨日はあいにくの天気で、今朝もまだ雨が残っていました。今日もそれほど良い天気にはならなそうですが、どうなることでしょうか。
先日とある雑誌で、本を読むのには体力が必要である、書く側は読み手を意識して推敲を重ね、編集社の校正等も入るなどしエネルギーが入ったものだから、旨の意見を目にしました。昨今のSNS等の乱用による世間の騒動に対し、一石を投じたものだったように思いますが、正鵠を射たものだと思い、心に残りました。
ある程度の文章を書いた人はわかると思いますが、書くには大変なエネルギーを必要とするものでして、一度やるとやりたくないと思うほど、直後はおなか一杯になります。おなか一杯の意味ですが、例えば論文一つ書くにしても、自分のテーマに関する、出版され存在している文章はすべて読まなければならず、出版されていないものについても、あらゆる手を使ってリサーチし、研究に漏れがないようにします。あらゆる視点からの検証もすんでいなければならず、論文に携わる指導教官やその関係者など、複数の専門家が目を通し、修正を重ねます。そしてやっと発表できる機会を得られるものです。この時点で頭の中はいっぱいいっぱいになって、他のことは全く考えられないほど、夢に出てくるほどになります。おなか一杯とはそういう意味です。
この世界を一度知ってしまうと、軽々しく、専門的な意見を言えなくなるほどです。
著名な研究者はこのような世界を勝ち抜いてきた人たちです。むろん、多分、盗作や足の引っ張り合いなど、世間でおきている当たり前のことも、経験してきたうえでのことだと思います。
SNSは今世紀に登場した新たな自己表現の形であり、その存在を否定するつもりはないのですが、この分野における自制の在り方について、考えさせられることはたびたびあります。社会的な影響力を持つ方が、権力争いの中で利用していることもあるでしょうし、世論操作的に使っていることも、私自身、以前も書きましたが多く経験しています(興味のない著名人の情報が流れてくるなど)。それが良いことなのか。
そして軽率な使用によりよく炎上もしていますし、訴訟も起きていることは既知の事実です。
ただ、研究者や作家等文章を書くことを専門にしている方々の間で、訴訟が起きているケースというのは、あまり聞いたことがないように思えますし、あるとしても盗作であるとか、限定的なケースかも知れません。専門家同士の限定的な領域内での争いはまあ理解できますが。
もっとも著名な学者の方の中には、故安倍総理のことをく〇安倍とか死〇安倍とか言っていた人もいました。そんな人が今、手のひらを返したようにSNSへの自重を呼び掛けているのは、いかがなものかと残念に思います。
逆のパターンもあり、過去、過激な発言を「失礼である」と自重を呼び掛けていた方が、今や「〇そ〇そ」に発言していることもあります。困ったものです。飲み会での愚痴みたいな発言を公の領域でされている。
これらの現状をどうとらえるかですが、そういうものだと思って割り切ってみるべきでしょうし(あるいは見ない)、頭の中でカテゴリー分けして情報の使い分けをする工夫も必要でしょう。メディア等の方々も、報道する場合、ここは「平場」なのだと、報道のやり方を心がけるべきなのかも知れません。
平場はその人の器量を試す場なのであって、寄席における平場なのかと、間違いや行き過ぎはあるかと、一つの現象として右から左に流すくらいの姿勢が大切なのかも知れません。そんな意見をまともに報道しないことが肝要かも知れません。若手芸人が前座で話すような話を、期待して本気で聞きにくる人はあまりいません。そんな平場から、大物芸人を発掘する目を養うだけ程度の知識と、あまり真剣に考えない。この程度で良いのだと思います。
有識者であっても、業界の大物であっても、SNSの発言に熟達していない人は多いと考え、これは平場で起きていることと、まともに取り扱わないことです。
他方、著名人の方々を常々気の毒に思うのは、このような「軽い」意見が大きな流れとなって世論が形成され、批判につながることです。有識者や、業界の大物が行っていることですから、世論もより形成されやすくなるのでしょう。
結果、冷静に考えれば「大した事ない」ことであったり、人間社会では当たり前におきること、で苦慮させられることが多い。つらいことだと思います。
攻撃する側は、大したことではないのだから、と矛を収める勇気も必要なのかもしれません。平場なのですし、、、なんといっても明日は我が身なのです。
最近本を読むことが少なくなっていました。久しぶりにセミナーに参加して(最初は実績のある方々から)、文章が読めるスキルに戻しつつあります。
幸いにして頭の中は空っぽです。
本を読むのには体力が必要なのですから。
まずは体調第一。